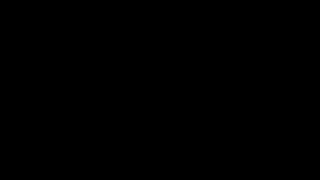 ①-復元例
①-復元例
3つの「龍図」その3・能生白山神社の龍図
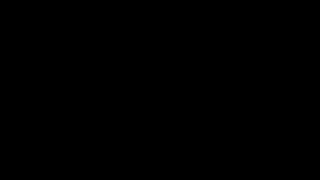 ①-復元例
①-復元例  1-復元系
1-復元系  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 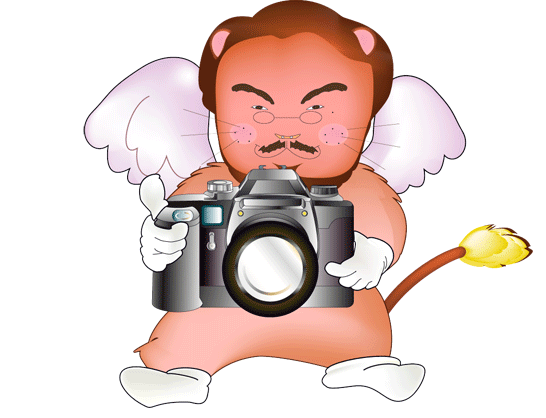 ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術 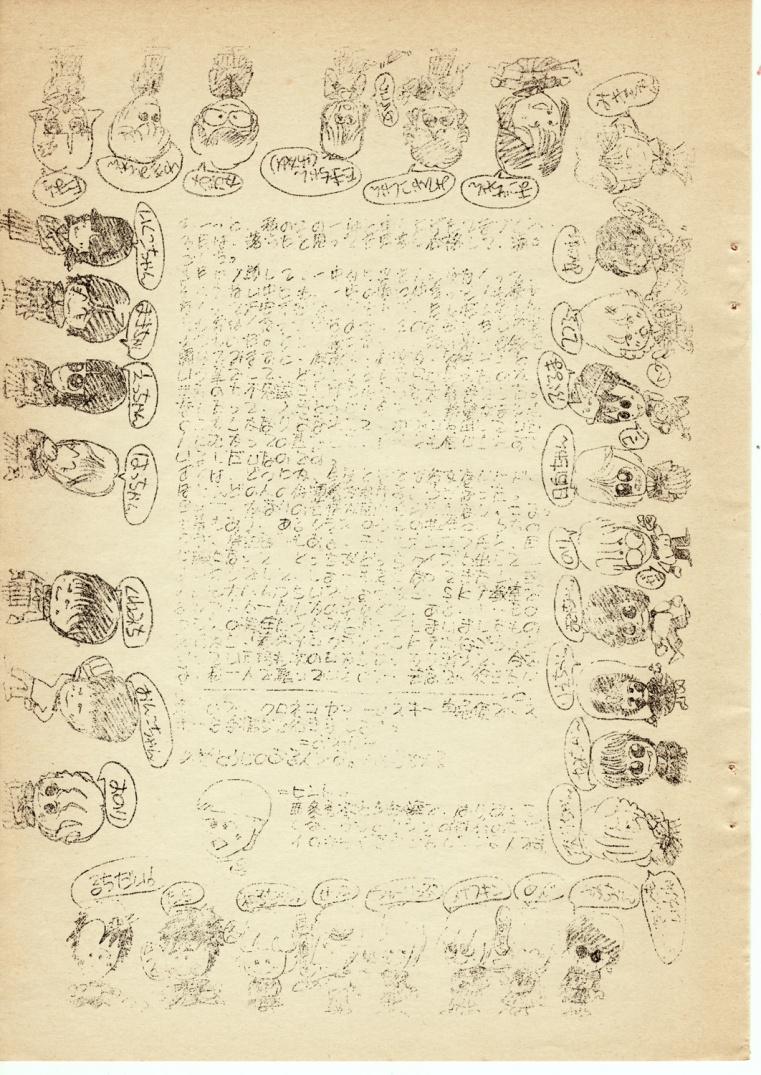 ①-復元例
①-復元例 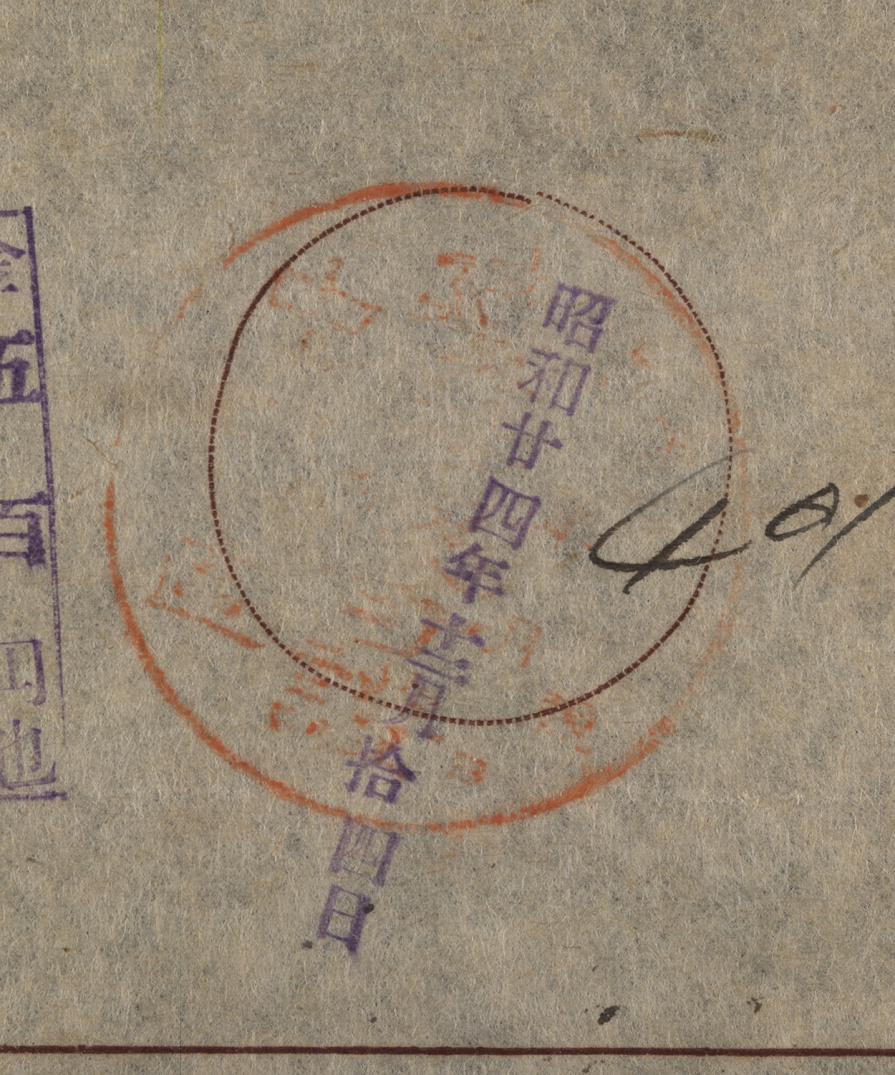 ①-復元例
①-復元例 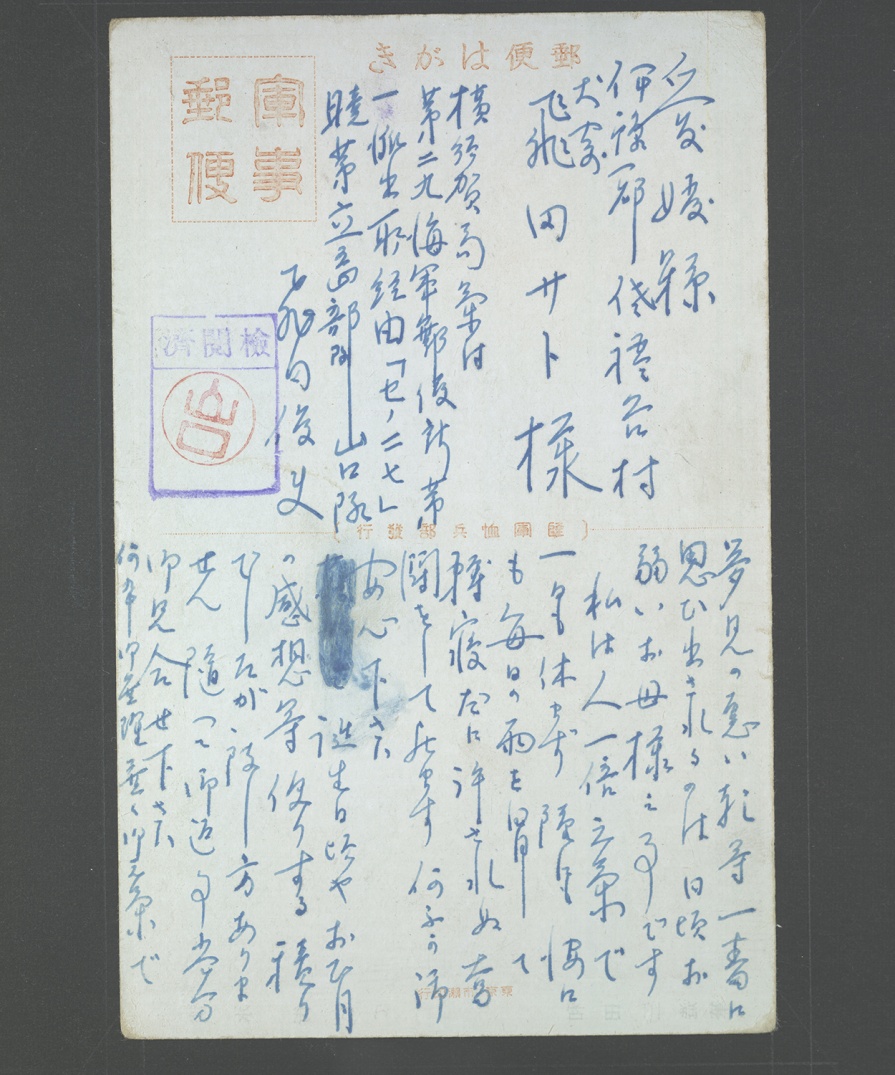 ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術 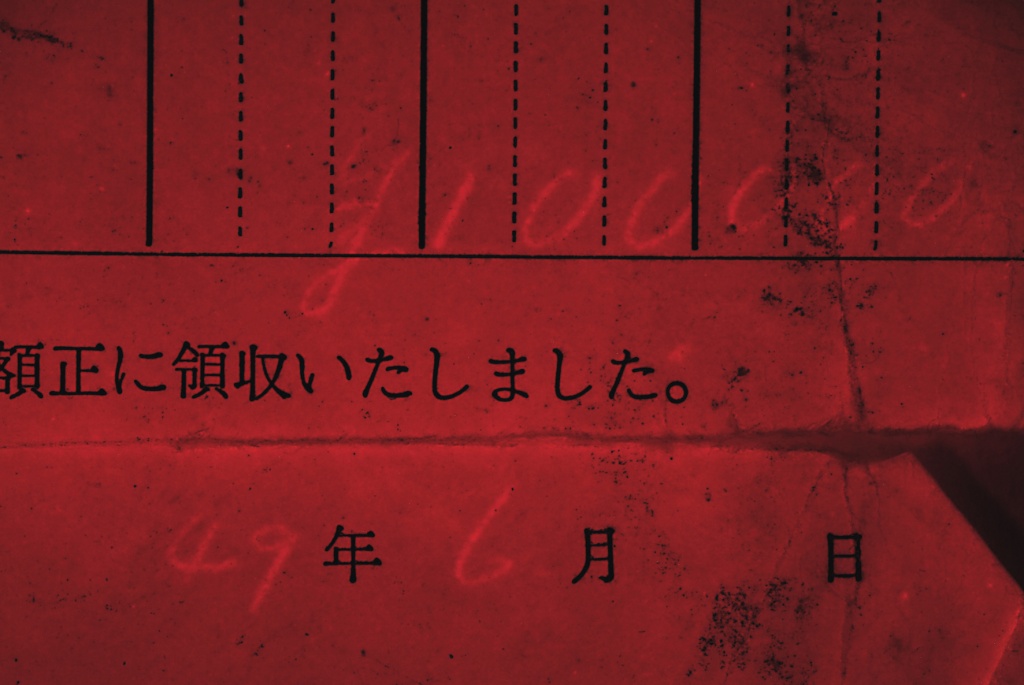 ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 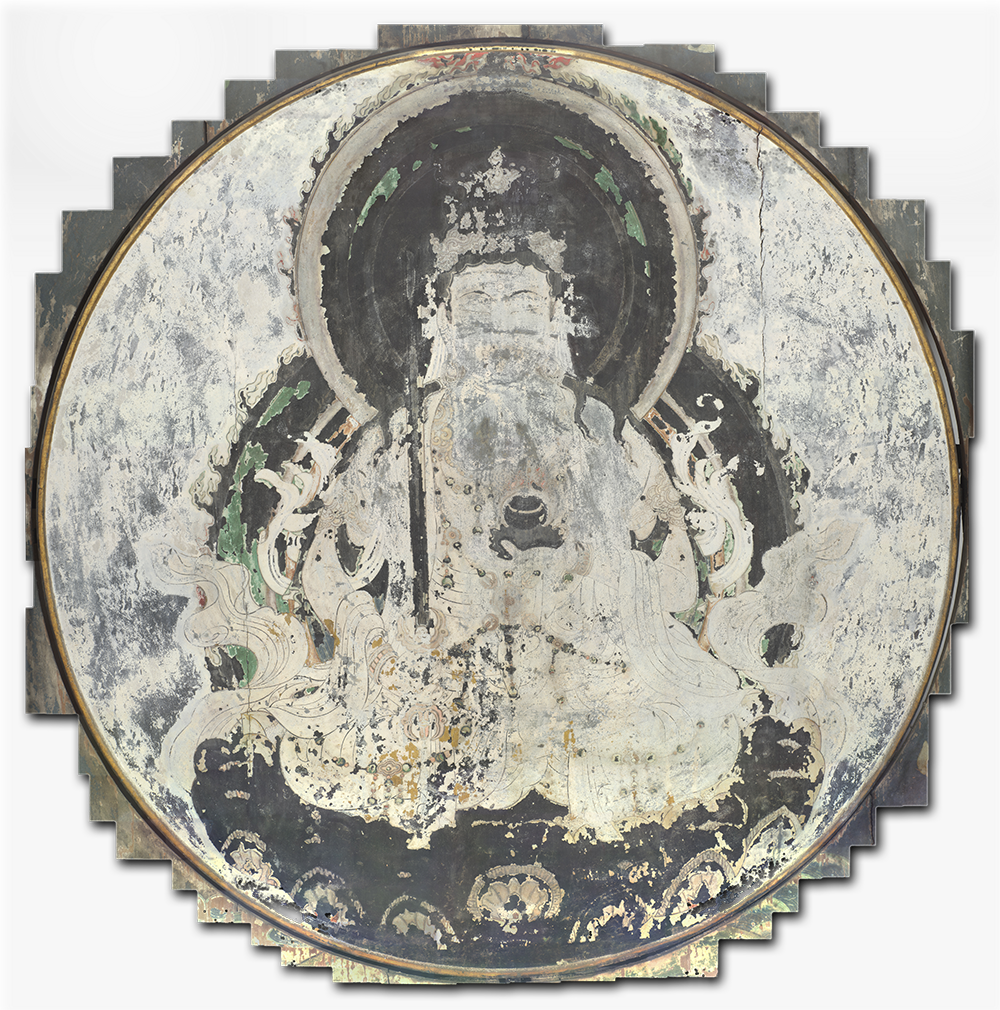 ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 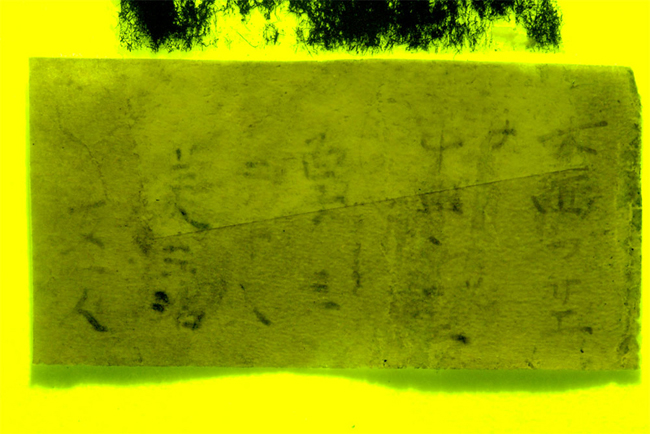 ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 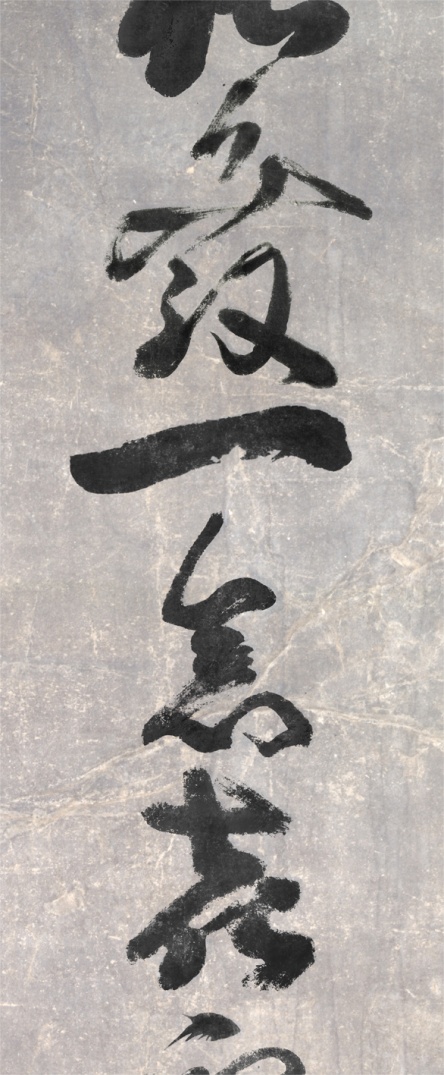 ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 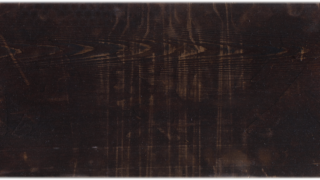 1-復元系
1-復元系  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ②-復元技術
②-復元技術 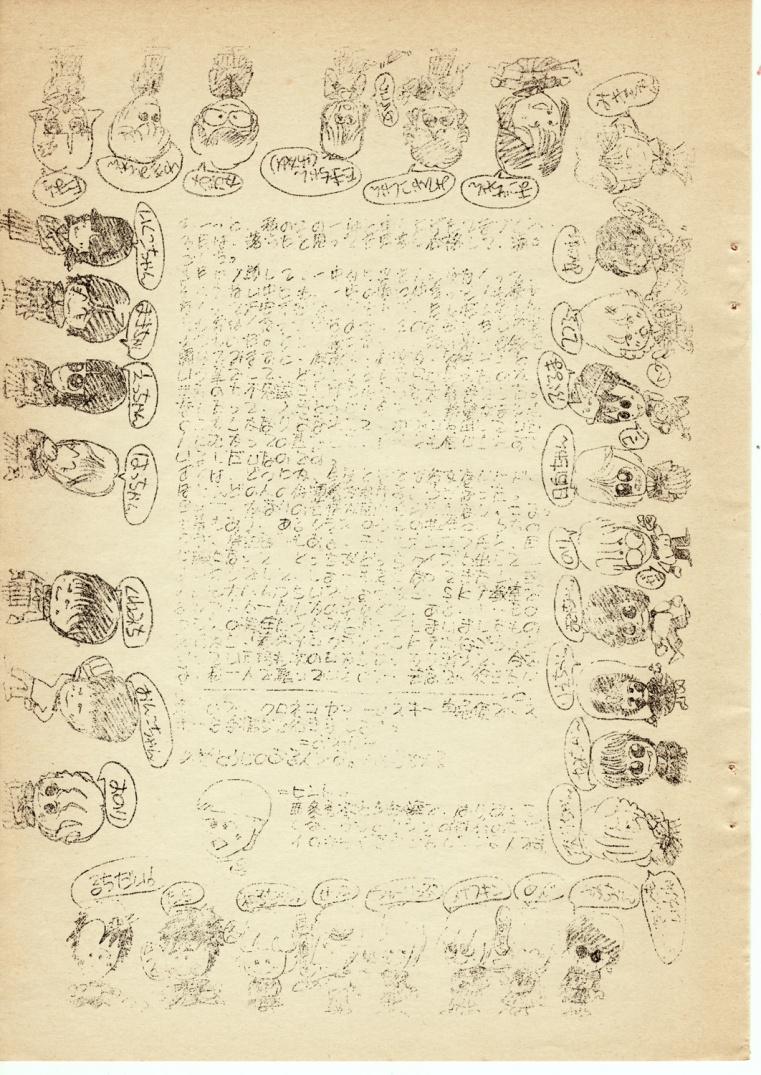 ①-復元例
①-復元例  ②-復元技術
②-復元技術  ①-復元例
①-復元例 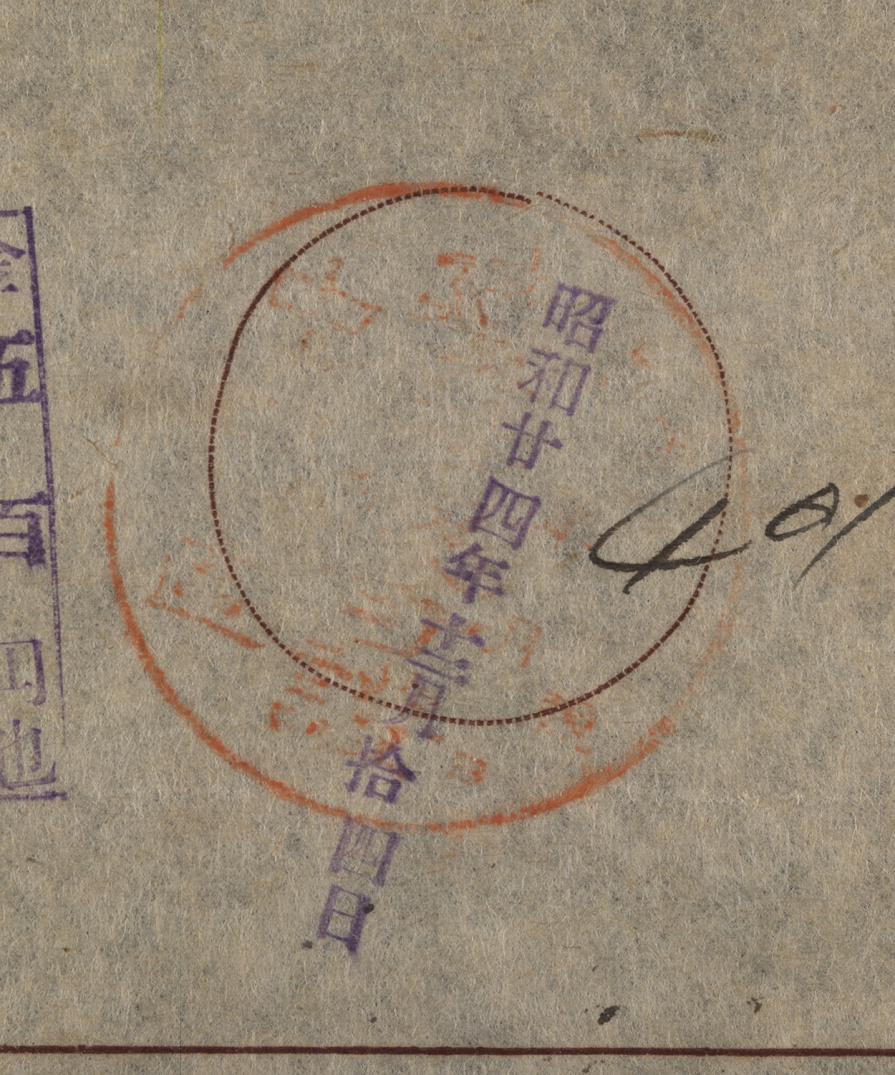 ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 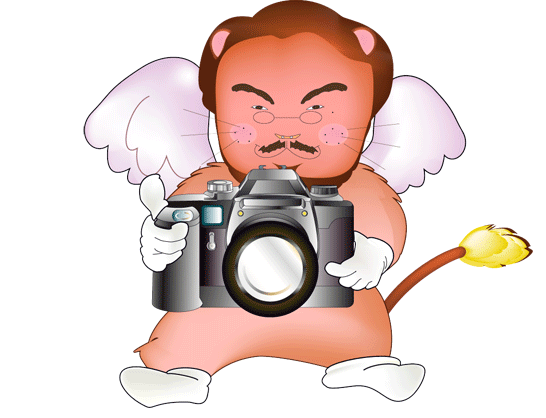 ②-復元技術
②-復元技術 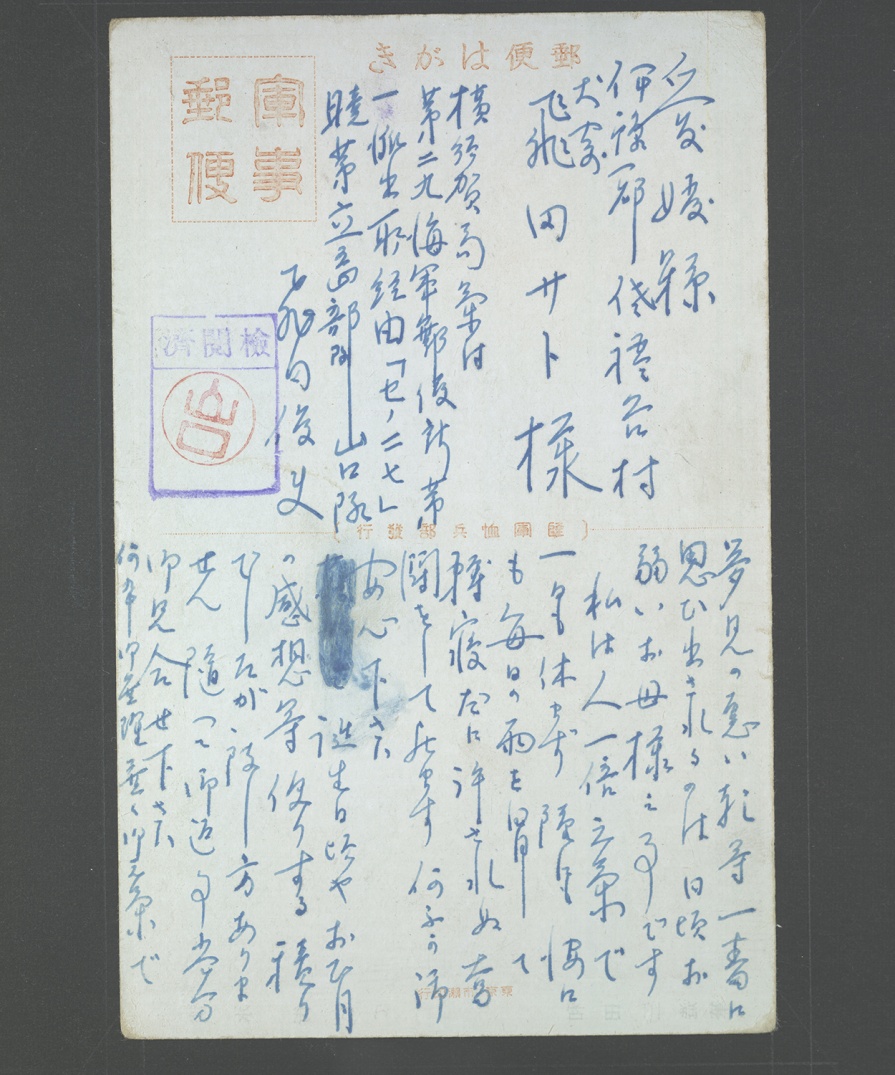 ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 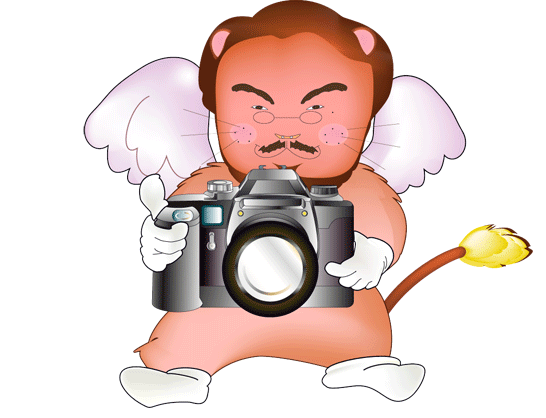 ②-共時性・不思議な話
②-共時性・不思議な話  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 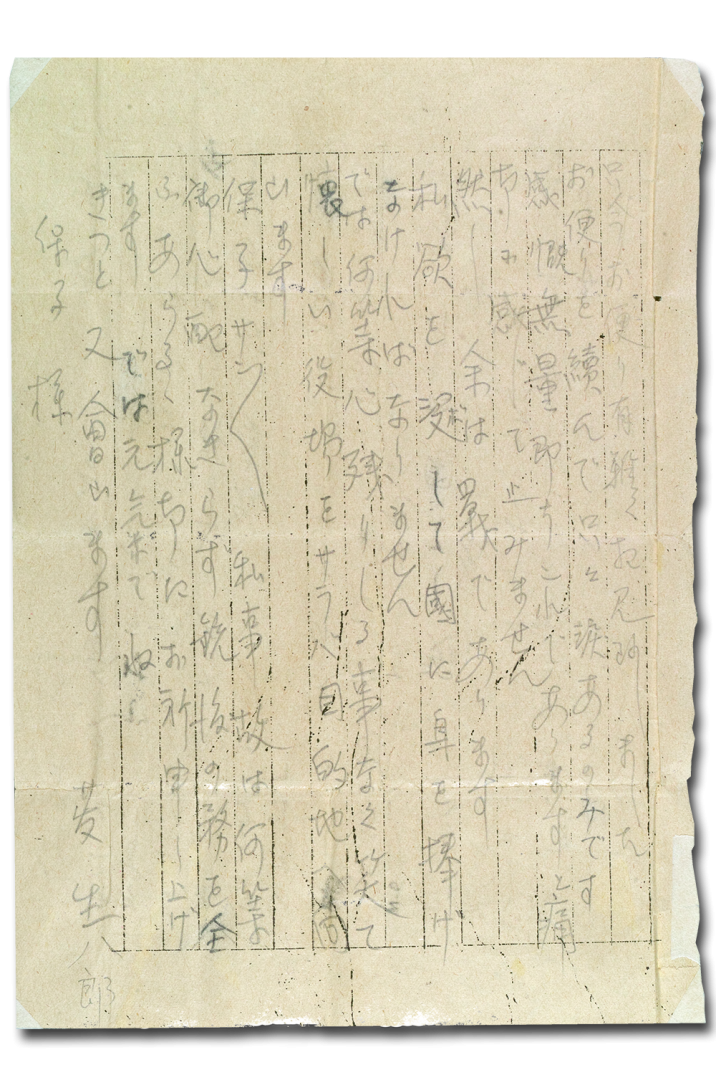 ①-復元例
①-復元例  ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 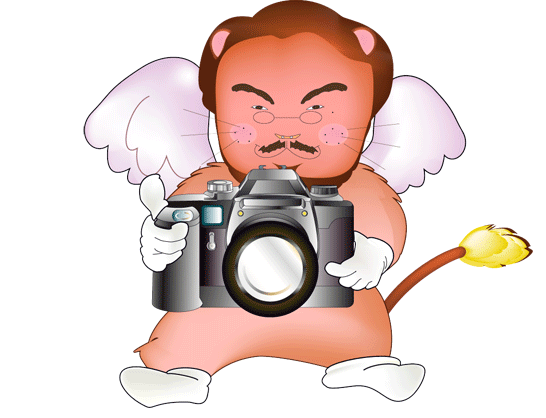 ①-復元例
①-復元例 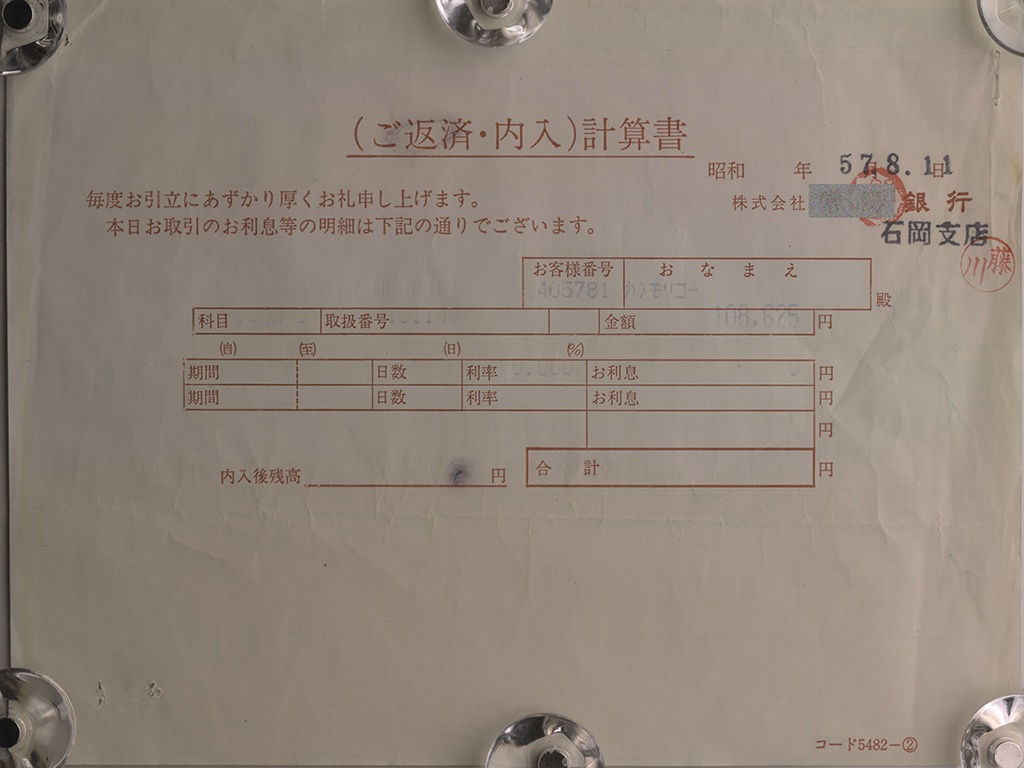 ①-復元例
①-復元例  ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術  ②-復元技術
②-復元技術  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 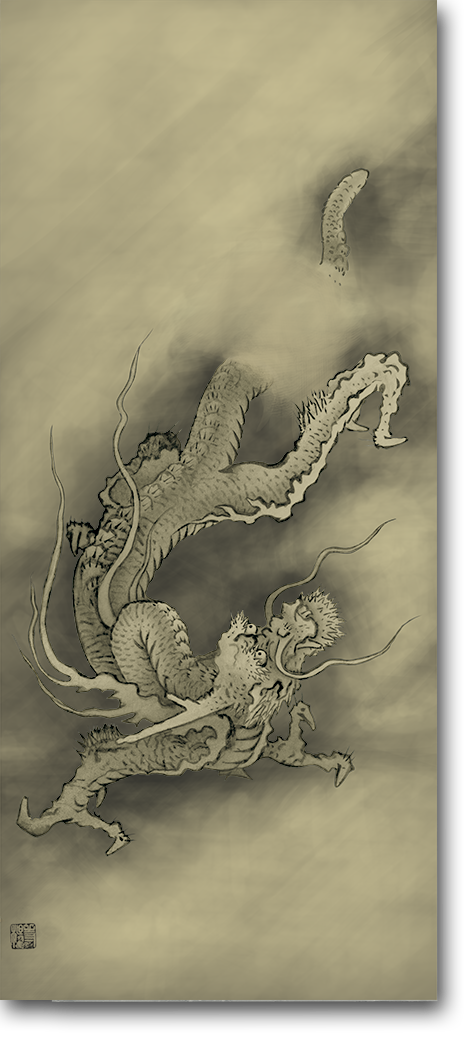 ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ②-復元技術
②-復元技術  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 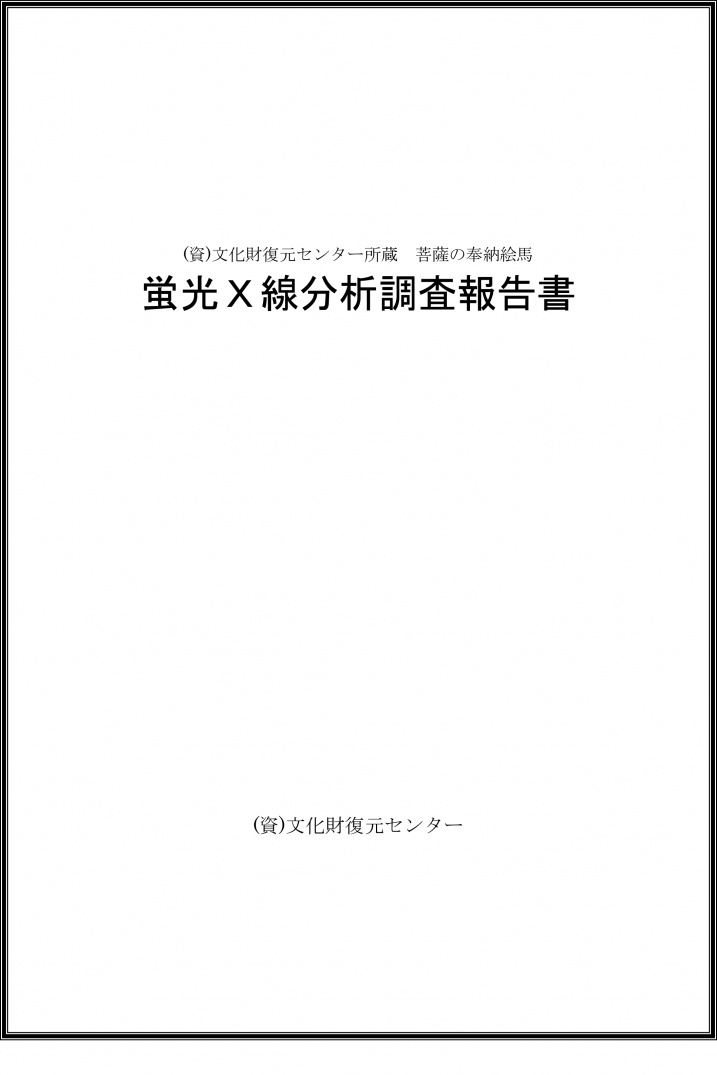 ②-復元技術
②-復元技術 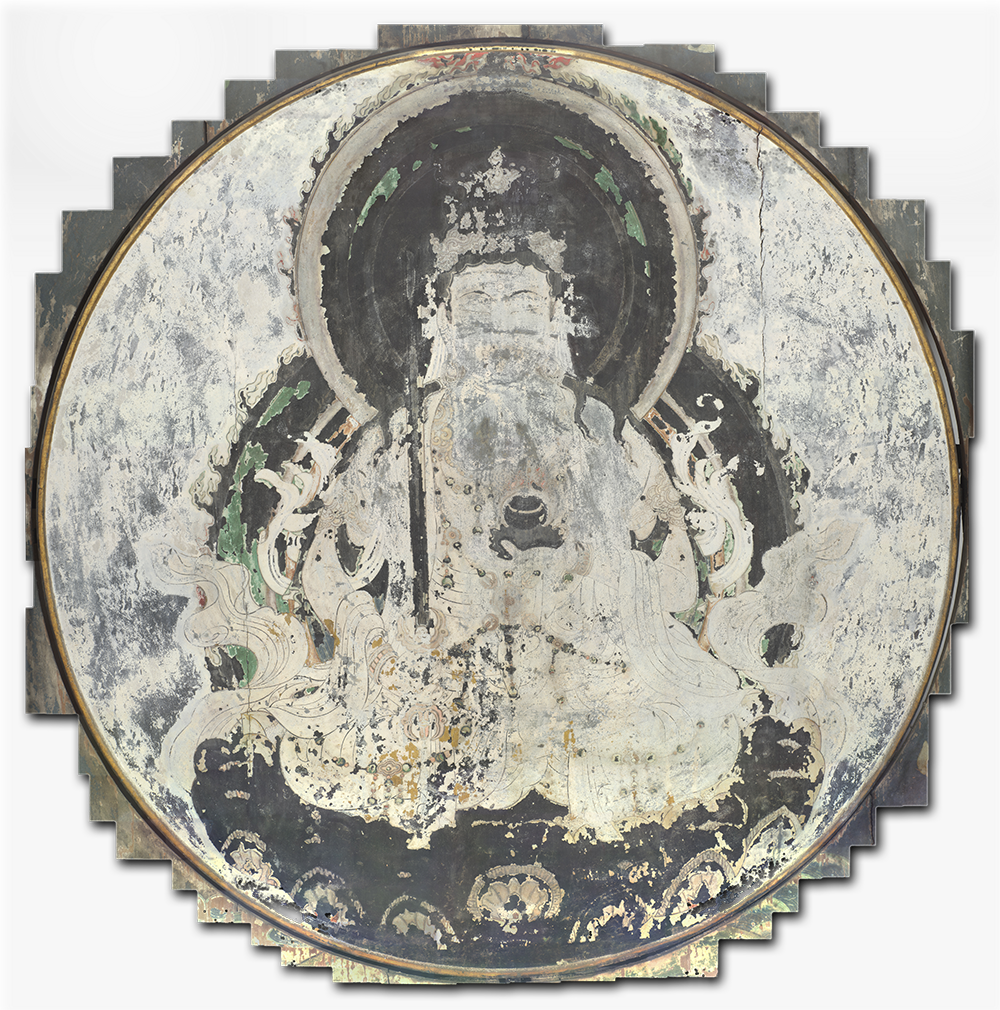 ①-復元例
①-復元例 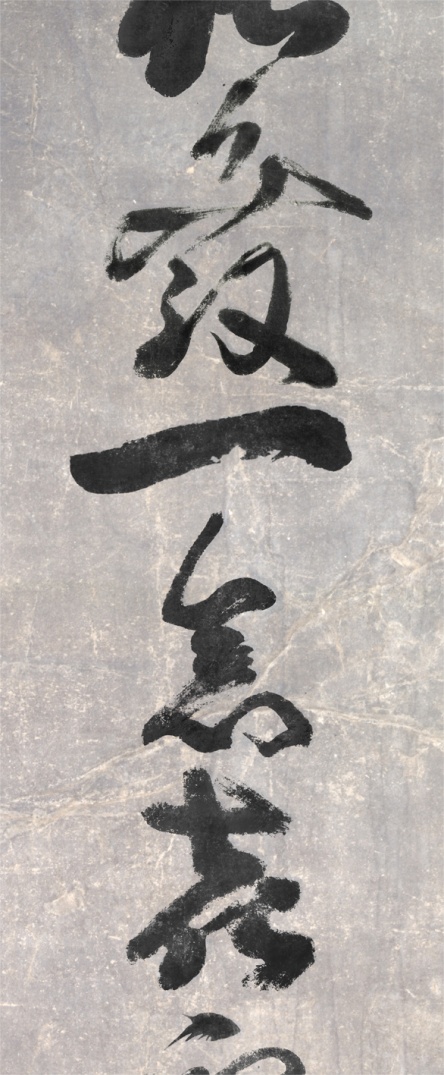 ①-復元例
①-復元例  ②-復元技術
②-復元技術  ①-復元例
①-復元例 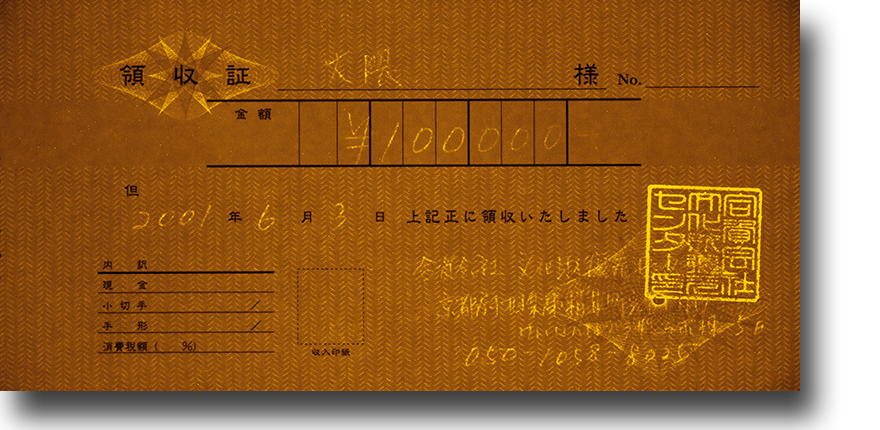 ①-復元例
①-復元例 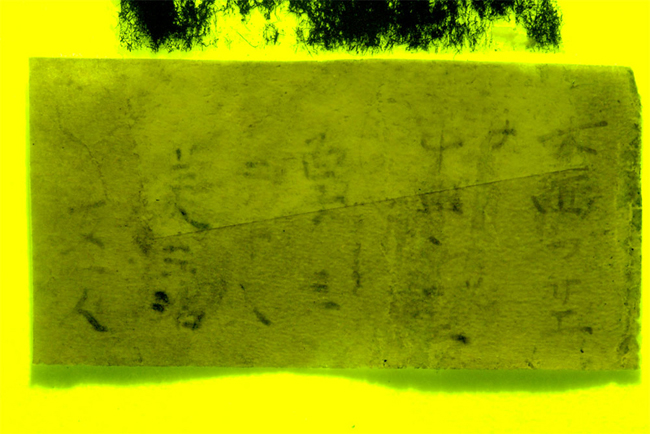 ①-復元例
①-復元例 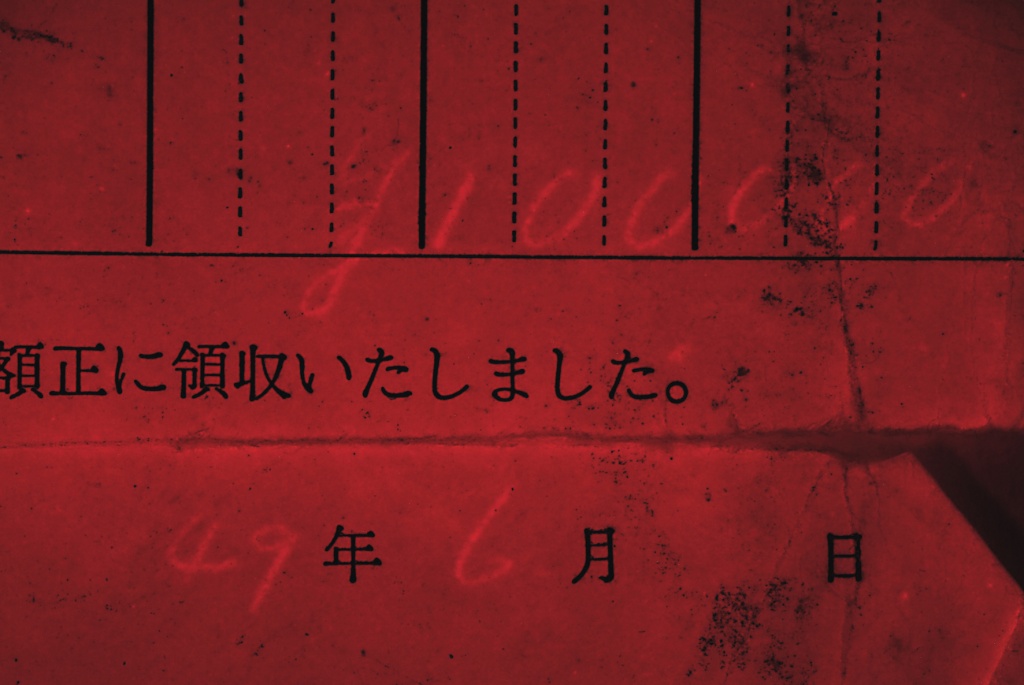 ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ②-復元技術
②-復元技術  ①-復元例
①-復元例 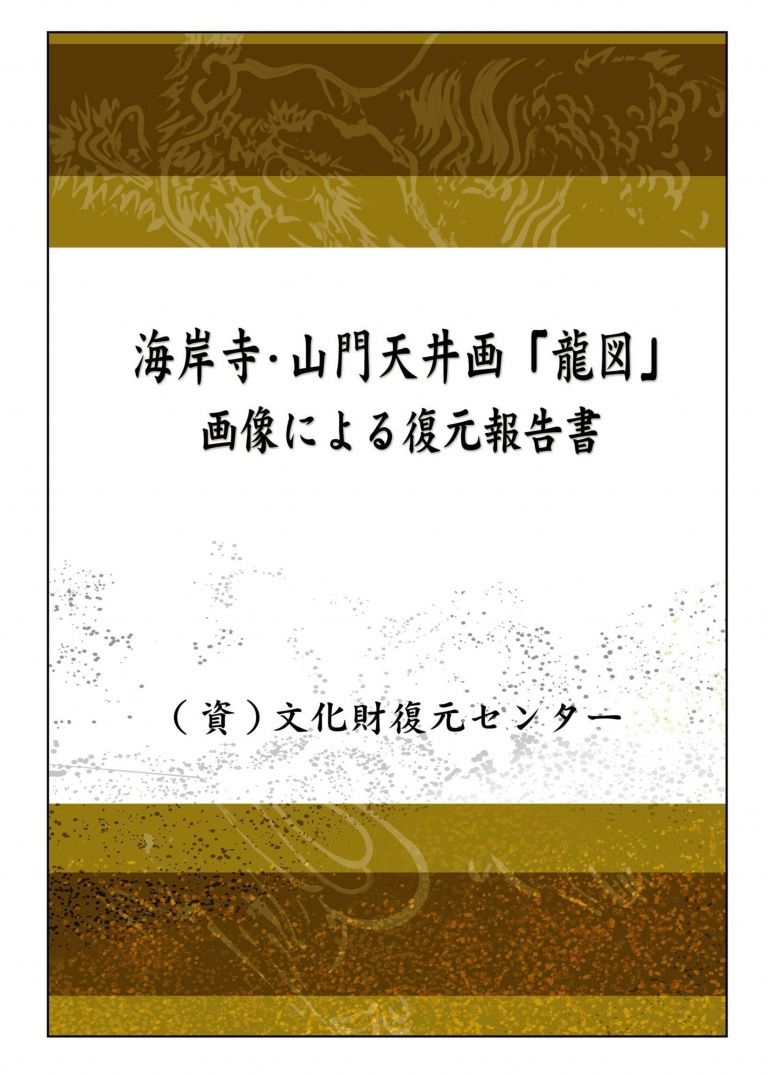 ①-復元例
①-復元例 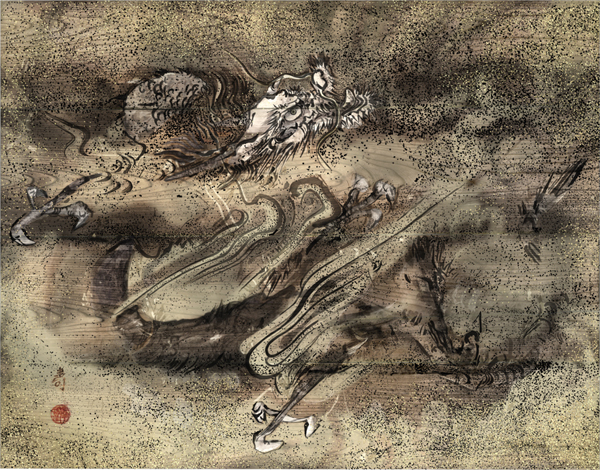 ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例  ①-復元例
①-復元例 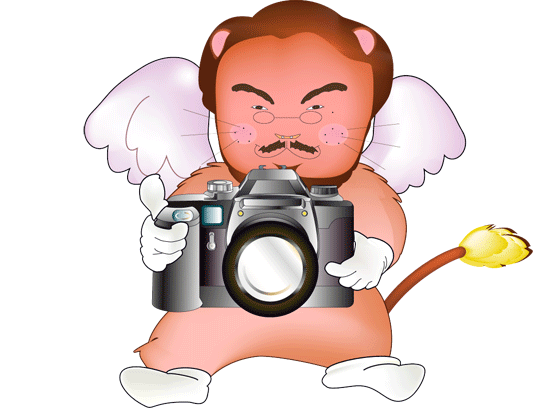 ②-復元技術
②-復元技術